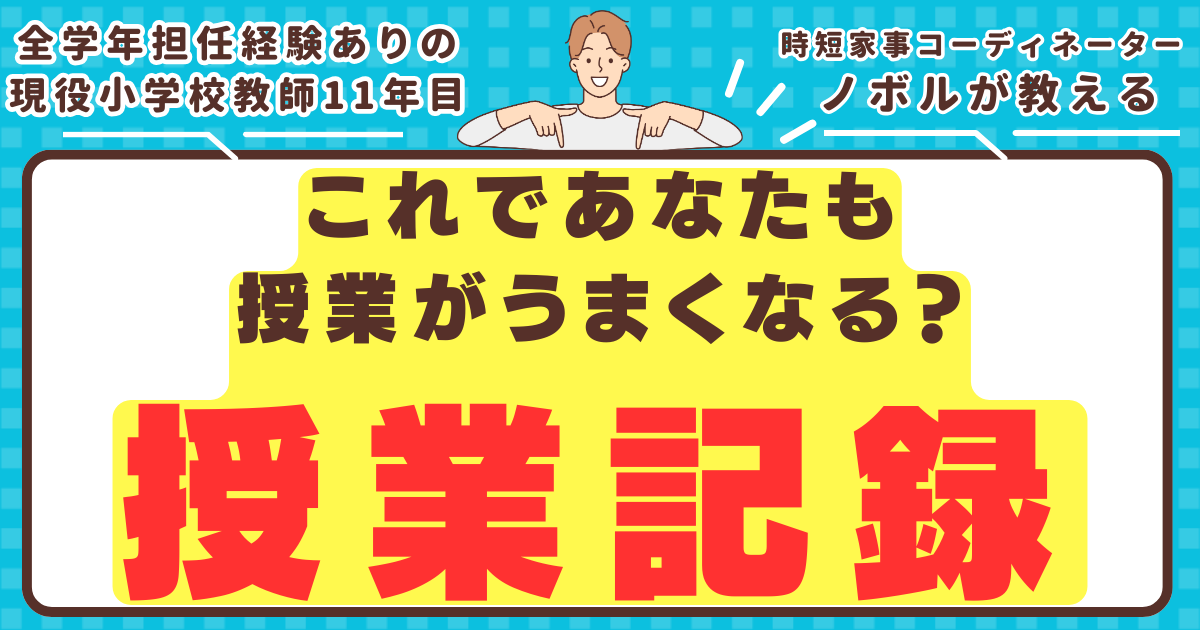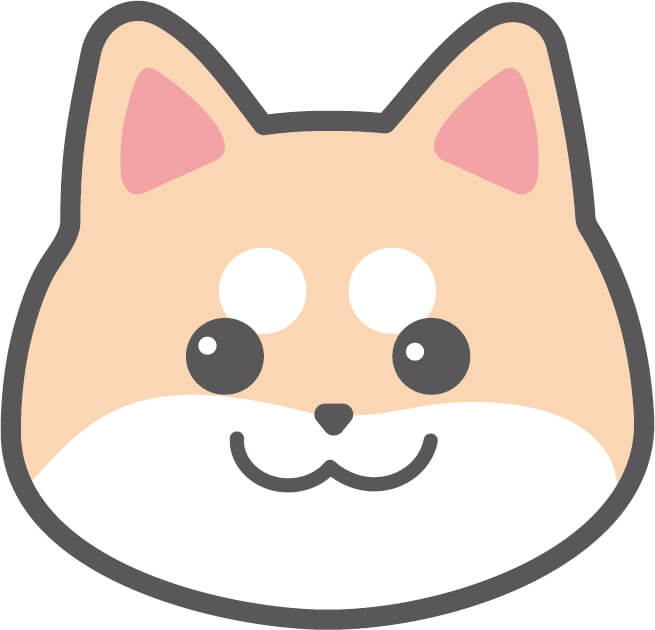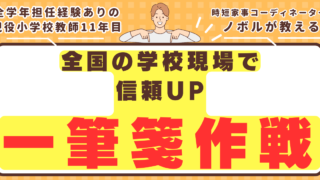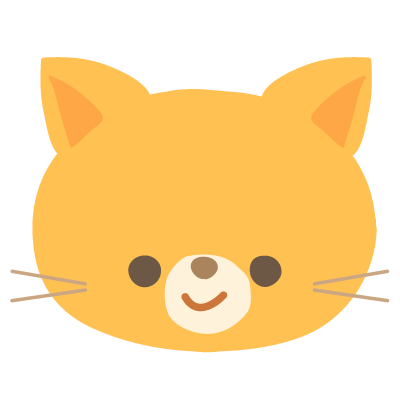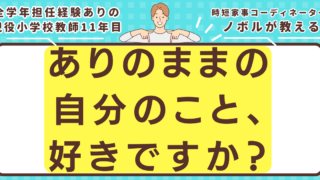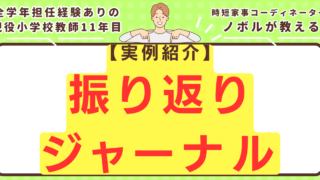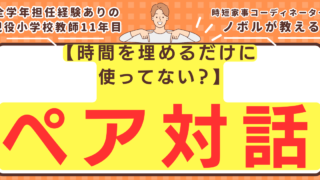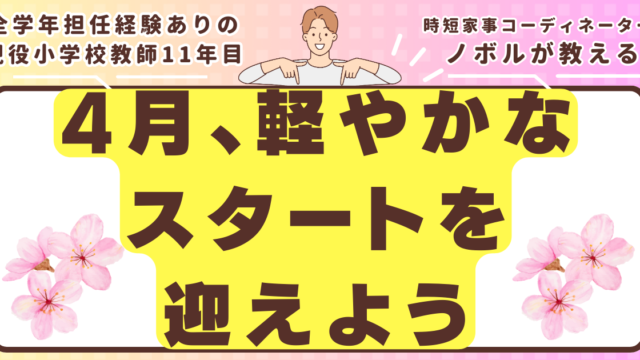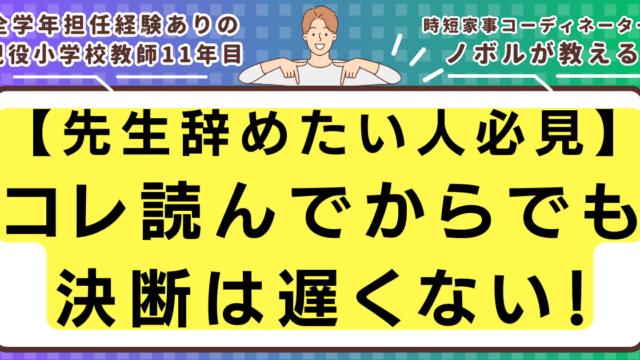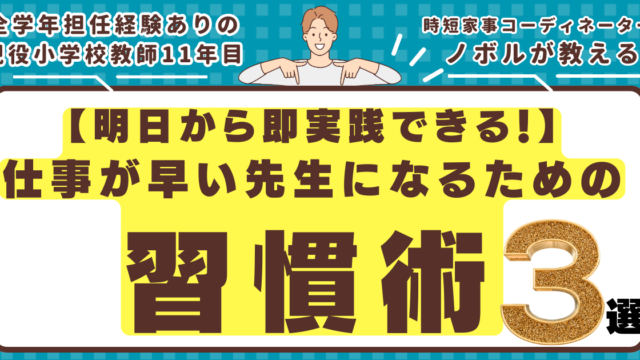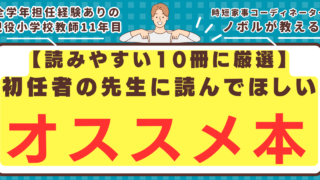こんにちは。
娘が縄跳びにハマり、家に自家製のジャンプ台をつくったら大喜びの娘を見て
ガッツポーズが止まらない、ノボルです。
ノボル先生、嬉しそうだね!
今回は、授業編です。
結論から言います。
授業がうまくなるたった一つの方法は
ノボルの習慣の一つである、「授業記録」です。
私は、毎年のクラスアンケートで「ノボル先生の授業はわかる」という項目があります。
- 今年・・88%(6年担任)
- 昨年・・88%(支援学級担任)
- 2年前・・90%(6年担任)
- 3年前・・92%(5年担任)
という結果でした。
もっともっと授業がうまくなりたいと思って日々過ごしています。
学校の先生は「教えること」が仕事です。
授業がうまくいかないと、子どもとの関係もうまくいきません。
授業が上手だと、子どもといい関係を築けます。
最初から授業が上手な人はいません。
授業が上手な人は、見えないところで努力しています。
この記事を読めば、授業に自信がない先生がこの習慣を取り入れることで、わかりやすい授業を展開することができます。
この記事は、こんな人に読んでもらいたいです。
- 授業が上手くいかない先生
- 子どもたちが「わかった!」と言うような授業をしたい
- 授業で勝負したいと思っている先生
ノボルが父親として、そして10年以上教壇に立っている教師として培ってきた経験をこの記事に凝縮しました。ぜひ、最後までお読みください。
あなたも、授業がうまくなるための努力をしていきませんか?
まずは、ノボルの自己紹介から!
- 『大人も子どもも笑顔になる』がモットー
- 現役小学校教師11年目。1~6年全学年担任経験あり
- Q-Uによる学級満足度90%越え
- 教育、ビジネス、自己啓発などを中心に年間100冊以上の書籍を読破
- 義務教育学校経験。小学校に所属しながら中1社会を担当経験
- 学年主任の経験
- 学級担任に加え、人権主担・生活指導部長・道徳推進教師など複数の校務分掌を掛け持ち
- 病休経験→働き方を見つめマインドを整え小学校教員として復活
- 娘と息子をもつ2児の父親『行動で示すカッコイイ父ちゃん』が目標
- 1年間の育短(週に3日勤務、2日を育休)経験
- 仕事と家事の両立をめざし、時短家事コーディネーター資格取得
- 30歳を機に、フルマラソン挑戦。以降、毎年フルマラソン参加。
授業がうまくなるためには「授業記録」を取れ!
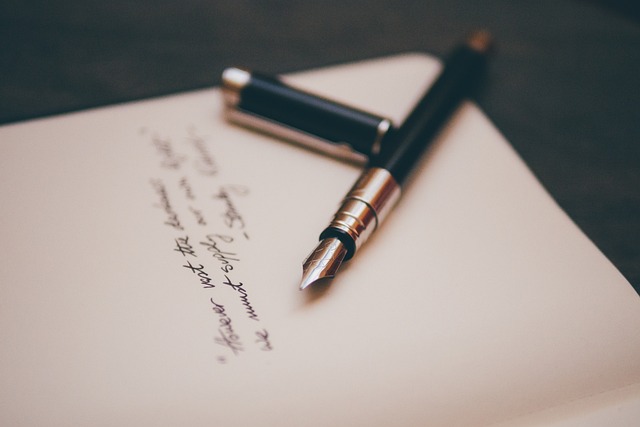
授業を思い出して、子どもの姿、発問、次どうするかを打ち込む
保存・保管ではなく、ブラッシュアップ
私は放課後に授業記録を打ちます。
授業記録とは何でしょうか。
授業記録とは、その日にあったことだけでなく、授業の中で子どもがどんな反応だったか、子どもと私とのやり取りなど、具体的に書いています。
誰に見せるものでもないので、具体的な子どもの名前も書きます。
目的は、「俯瞰で考えてみる」こと。
私は「次、同じ学年を受け持つことになったら使える」という意味で、授業記録はしていません。
未来の自分ではなく、今の自分、今の子どもたちにかえすため
このポイントは、大事にしているところです。
私は授業の中での気づきや改善点を自分の中で咀嚼するために授業記録を打っています。
教室で行うときには、ポメラというデジタルメモを使います。私にとってはなくてはならないアイテムになっています。
最近では我が子の保育園お迎えや出張が重なることが多く時間が取れないこともあり、音声メモを活用することもあります。
今回この記事を書くにあたり、これまでの授業記録を見返すことにしました。
ノボルの授業記録がどんなものかは、実物を見る方がイメージが湧きやすいと思うので、少し紹介しますね。
5月23日(月)授業記録
2時間目社会
みんなの意見を聞こうとしている意識は定着しつつある。例えば友だちが話すときに正対をすぐするHさん。一番前の端からでも聞こうとするKさん。育ってきたな!
7年社会で授業をしているときに気になることがある。Sさん、Sさんの声がみんなに聞こえない。
先「Iさん、Sさんが何と発表した?」
Iさん「聞こえません」
先「Sさん、聞こえなかったみたいだからもう1度どうぞ」
Sさん「○○だと思います」
先「みんなはどう?話せる人手を挙げます」 「7人」
これはSさんの声を大きくする手だてをすべきか。もっと周りが聞くように耳を研ぎすますよう声をかけるべきか。
自分としては、今の手立てはこうしよう。
①はきはき発表できているHさん、Nさん、Aさんあたりをほめていく
②「さんはい!」をひたすら行い、発表の声の大きさを全体で鍛えていく
でやっていこうと思っている。
ただ、これが正解なのかは実践を積み重ねていくのみ。
今、改めて読むと、授業の中での自分の葛藤も文章にあり、この子たちとの情景が思い浮かびました。当時、義務教育学校に勤めていて、私は小学校教員でありながら、7年(中学校1年)社会を担当したときの授業記録です。
5月ということで、子どもとの授業の中で「聞き構えをつくる」ことを念頭に置きながら授業をしていた時だと思います。
そして授業記録を打っていると、
- 「あっ。Aさんが以前よりも成長している!」
- 「班の中での協力が光る」
など、子どもの成長やプラスな行動を見つけることができます。
その眼を養う効果も実感しています。
そんな、ポジティブな姿は本人や保護者の方に伝えたいですね。
やはり、授業記録を打つことの意味は大きいですね。
授業記録を打つと、授業の中での自分の発言に意味が生まれます!
自分の授業を録音して「聞く」
自分の授業を録音して、子どもになったつもりで聴いてみましょう。
はじめは、「拷問か」と思うぐらい、恥ずかしすぎて最後まで聞けないと思います。
はじめはそれでいい!はじめの導入だけでも聞いてみよう!
これは、授業の内容というより、授業をする基礎・基本を確かめる意味合いが強いです。
どれだけ経験を重ねても、基礎・基本に忠実に行うことが授業がうまい先生の本質。
特に、こんなことをチェックしながら自分の授業を客観的に聴いてみよう。
そして、気づきを授業記録していきましょう。
- 声が大きすぎないか
- 子どもに声が届いているか
- 子どもの意見を復唱していないか
- 教師が話す時に、子どもがザワザワしていないか
- 声が低すぎて、威圧感を与えていないか
- 言葉の語尾が聞き取れるか
- 発問があいまいでないか
- 「えー」とか「あのー」とか、関係ない言葉を連発していないか
- 子どもの発言の意味をくみとれているか
経験を重ねても、初心を忘れずですね。
自分の授業を録画して「見る」
自分のしゃべりだけでなく、総合的に授業力をアップしたいと思ったら、自分の授業を録画することです。
研究授業を行うことでも、授業力がアップしますよね。
それと同じことです。
録画するだけで、緊張しそうだニャン!
おっしゃる通りで、録画するだけで緊張しますよ!
でも、それだけでいつもの自分の授業よりいいものになります!(笑)
ノボルは、ここ5年連続で校内の研究授業か、または市や校外の研究授業を引き受けています。
それは、「授業で勝負する先生であり続けたい」からです。
逆を言うと、自分の授業を俯瞰でみる機会はなかなかないものです。
そのために、まず自分でできることは「授業録画」です。そして、録画したものを見ながら気づきを授業記録するのです。
ちなみに、録画を見る場合は、総合的に見ていくと、気づきが膨らみます。
- 授業のねらいが明確か
- 教師の発問からの子どもの反応
- 板書
- 机間指導
- しゃべるときの目線
- 教師の立ち位置
- 自分の変なクセ
私は無意識に、教室の右側で話すことが多かったですよ。撮ってみてわかることってとても多い!
文字起こし・テープ起こしをしてみる
文字起こしは、正直時間はかかります。ですが、コレを一度してみると、今後自分が授業をする時に意識が変わります。
教師という仕事はやることがたくさんあり、毎日が多忙です。
ですから、この文字起こしを何度もできることではありません。
だからこそ、一度だけでも試してみることで授業への意識改革をしましょう。
私が以前に行った授業の文字起こしを紹介します。
45分の1本の授業全てを文字起こししてみました。
あまりに長いので、今回は導入の数分のみのものとします。
その下には、自分の気づきを書いています。
恥ずかしいですが、今回は特別ということで!
2・3時間目 4年社会
先「今日は、えっと、写真を持ってきました」
子「なになに?」
Sさん「あっ。先生、それ家にあります!」
先「待て待て。全部見せますので、それから発言しましょうね。」
私が、見せたものは日本のモノとは違うものをあえて見せた。
先「見たことある人はいますか?」
子ども10人以上、
先「見たことがない人は?」
子ども10人以上
先「実は、昨日行った大阪欄間と関係があります。この中で、いや、この写真から、何か気がつくことをノートに箇条書きで書きます」
子ども、ノートを開ける
文字起こしなので、録画をそのまま書いています。途中で、「いや、」などは本当にリアルですね。これこそ、自分を磨く術です。
次は、この文字起こしをしてからの気づきです。
昨日、大阪欄間の聞き取り学習と制作体験を行い、伝統工芸士さんが5人もきていただいた。そこで、今日の目標は「大阪欄間体験の感想を交流しよう」だ。3学期になり、聞く文化が定着したこのときに、自分たちで意見を議論し、交流させたいと思い設定した。感想を書かせ、自由起立の形式でスタート。口火を切ったAさん、すばらしいな!まずほめた。どんどん発言し、私は板書でまとめる。今回の授業ですごい!と思えたところ、ここまでの仕掛けが活きたところが3点ある。
①友だちが発言した後、Aさんが質問で手を挙げた。この子供同士のやりとりができるようになってほしかったのでGOOD!
②進行中にSさん、Yさん、Kさんが黙々とノートにめもをとっている。友達の発言から自分の学びに落とし込んでいる姿。見事!ここまでメモを重要としてきた1年で、教師が言わなくてもできている姿を授業終わりにみんなに広めた!
③Sさんが3回目の発言で「先生、話があります」と話した。すると、「少し前の日本と外国の話なんですけど、そもそも外国とつながりってあったんですか?」とみんなに問いかけた。そこでみんなは「えー。どうかな~?」と考え始めた。何人かは手が挙がる。
これやねん!追い求めていたのは!ここから、話の熱は高まってきた。「私は外国とつながりがないと思います」「私はあると思います。」など、すごく活気が生まれた。子どもが前のめりになる瞬間。こういう授業をこれからもどんどんしていきたい。
こういう微細な空気を掴めるのも、授業記録を積み重ねていけば、自然と身につくものです。地道な努力なんですよね。
師範授業を見学に行く
まずは、自分と同じ学校の先生や学年の他の先生の授業を見学させてもらいます。
私の経験上、人柄も授業も素敵な先生ほど歓迎してくださりますので、
断られる事もあまりないかと思います。
渋る先生もいますが…(^^;;
そんな時は無理せず全ての先生でなくとも、快く見学させていただける先生を選んで見にいきましょう!
そこで、終わってほしくないのが今回お伝えしたいところです。
自分の自己肯定感をあげる方法の一つに、「本に触れる」があります。
本は、その方の想いや考えを安い値段で知ることができる優れもの。
例えば、手に取った本の著者がされている実践を「五感で感じる」ことが、とても刺激になります。
1年間の間に公開授業や研究会で授業をされることがあると思うので、自分磨きだと思って時間とお金をかけてでも見学に行く価値は大いにあります。
私も毎年1回以上は、校外の公開授業に行きます。
最近では同業者である妻と一緒に、ある学校の公開授業に参加しました。帰りには、2人でランチもできますね!
実践に触れることと熱量を高めてくれる機会にもなるので、ぜひ!
子どもの意見を聞く
授業をしている側の先生と、授業に参加している子どもで感じていることが違うことも。
何より大事なのは、「子どもが授業に参加できているか」です。
どれだけ先生が上手に話しても、
どれだけ先生が上手に授業をしても、
子どもたちが授業に参加していなければ、
授業が成立しているとは言えません。
毎日でなくとも、子どもに授業について聞いてみるのも一つです。
私は、振り返りジャーナルのテーマで「〇〇の授業どうだった?」にすることがあります。そこで、子どもがどう感じていたのか、授業がわかったのかなど、子どもなりの言葉で返してくれます。
子どもが自分の成長のために書き記す、「振り返りジャーナル」についての記事はコチラ!
その言葉こそ、本物です。
その言葉をもとに、自分の授業記録とするのです。
席の隣の人とトークしてもいいですね。
- 今日の授業でわかったこと
- わからなかったこと
- 次知りたいこと
ペアトークだと、すぐに取り組むことができますね。
授業の中でよくみられる「ペア対話」についての記事はコチラ!
また、子どもたちには、学期の最後に「通知表」を渡しますよね。
私は、子どもたちに「ノボル先生への通知表」を書いてもらいます。
書かせる前には、このような条件を伝えた上で、安心して書いてもらいます。
- 成績に関わることではない
- 授業がもっとわかりやすくなるために先生があなたたちの本音を知りたい
- 誰にも見せないこと
安心感がなければ、子どもが思ったことを素直に書けないですからね。
授業がうまくなるための方法 まとめ

- 授業記録の目的は、保存・保管ではなく今の自分のブラッシュアップ
- 授業録音・授業録画で自分を客観的に見ることができる
- 目の前の子どもから学ぶこと
いかがでしたか。
学校の先生は「教えること」が仕事です。
授業がうまくいかないと、子どもとの関係もうまくいきません。
授業が上手だと、子どもといい関係を築けます。
今日が人生で一番若い日です。
授業がうまくいくことは、年齢や経歴に関係なく、習慣によって上達します。
ぜひ、今回の記事を試してみてくださいね!
以上「誰でもできる!先生が授業をうまくなるための、たった一つの方法」の話題でした。
ほいじゃあね~👋